2025年現在、小学4年生になる息子は小さい頃からぐずり、癇癪が激しい子です。
そんな長男のぐすり癇癪が、これまで以上に激しくなったのが彼が9歳6ヶ月頃からでした。
そんな中、発達検査を受けてみてはどうかと提案されましたことがきっかけとなり、2025年の夏息子が10歳2ヶ月の時に発達検査を受けることになりました。
この記事では、長男が発達検査を受けるまでの経緯と、発達検査を受けてわかったことをお伝えします。
長男のぐずり・癇癪で、家族全員が疲弊する日々
我が家のは息子を含め、3人の子どもがいます。
息子は第一子の長男であるため、私にとって初めての子育て。小さいうちはぐずりや癇癪はどんな子でもあるもの、私の慣れない子育てが原因で長男がよくぐずるのかなと思っていました。
2人目、3人目と育てるうちに、息子の癇癪の激しさが下の子とは比べ物にならないと気づきます。
これまでの定期検診などでは、発達について指摘されることもなく、これまでにあらゆる子育ての窓口で息子の癇癪について相談してきました。
しかし、具体的な解決策など見つからず、本人の性格的な要因と思われたため、うまく付き合っていくしかないと過ごしてきました。
ぐずりや癇癪がこれまで以上に激しくなった頃、息子は一日中、ご機嫌に過ごすことがなくなり、常に機嫌が悪くちょっとしたことがきっかけで癇癪を起こすようになりました。
そんな日々が何ヶ月も続き、息子がぐずぐず文句を言い出すと「また始まった…」と家族全員が疲弊していきました。
一見するとただのわがままのように思えて、『いい加減にしなさい!』と叱っても逆効果。何より、原因不明のモヤモヤやイライラを、癇癪を起こすことでしか発散できない長男が一番苦しんでいるのです。
そんな息子の姿を目前に、母親としてその行動の意図が理解できず、愛情がすり減っていくような日々でした。
息子の言葉から見えてきた“原因不明のモヤモヤ”
連日のように癇癪を起こす息子でしたが、特に登校前の朝の時間には、母親である私の『いってらっしゃい』の一言がきっかけで、癇癪を起こしパニック状態になることもありました。
本人に学校へ行きたくないのか尋ねると、学校には行きたいといいます。
当時は遅刻をしたくないから早く登校したい、だけど気持ちが整わないので登校できない、始業時間が迫ってくることに焦りさらにパニックを起こす、癇癪がヒートアップして母親にあたり散らす…
こうなると、私になすすべはなくただただサンドバックになるしかありません。
自分の精神を正常に保つべく、必死で目の前に人参をぶら下げていました。(この癇癪を無事に収束させたらちょっと高い化粧品を買おう…今晩は第三のビールじゃなくてスーパードライにしよう…など)
本人いわく、「わけのわからないイライラやモヤモヤが常に体の中にある」らしいのです。
そのイライラやモヤモヤがあると、お母さんが嫌がること(新しい鉛筆を折る、割と最近買ったプチプラ以外の服をビリビリにするなど)や、暴言(くそBBA!なんかまだ可愛いもの…◯ね!や、お前のせいで俺の人生最悪だ!など)を吐くことでしか発散できないとのこと。
感情のコントロールがうまくできず、自分が一番苦しいのだと打ち明けてくれました。
一見するとただの「わがまま」ではないか…とも思いましたが、それだけでは片付けられないかもしれないという気持ちで相談する先を探し始めました。
長男のぐずり癇癪とは長い付き合いなので、これまでにもあらゆる子育て相談の窓口に問い合わせしてきました。
しかし、自宅以外の場所では感情のコントロールができており、学校や幼稚園生活も問題なく、友人関係も良好、癇癪をおこすのは自宅だけということで問題視されることがありませんでした。
その経験から、私も今更相談先はない、相談しても結局本人の性格によるものでうまく付き合っていくしかないと半ば相談することを諦めてたところもあったと思います。
「発達検査を受けてみよう」と決めたきっかけ
息子の癇癪がなかなか収まらず、下の子の幼稚園の役員会を遅刻することになったことをきっかけに、幼稚園のママ友に長男の癇癪で困っていることを初めて話しました。
そうすると、同じように繊細な気質がゆえ癇癪が激しく漢方を処方してもらっているといった話や、発達検査や学力検査を受けた結果、発達に特性があることがわかり療育に通ったことで癇癪が治まったといった話を聞くことができました。
この時に感じたのは、声に出して助けを求めることの大切さです!
声をあげたことで、こんな身近に同じ悩みをもつ仲間がいてくれたなんて✨️(涙)と、とても心強く感じました。
ママ友から、絶対に一人では抱えきれないから手助けしてくれる人を探したほうがいいと教わりました。
それから地域の子育て支援施設、心理士、こども家庭センター、かかりつけの小児科、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーに相談し、現在も継続して相談に乗っていただいています。
相談する中で心理士さんに、外からはわかりづらい本人の困りごとに気づくきっかけになるのではないかということで、発達検査(WISC)について教えていただきました。
もちろん心理的ハードルもあり、すぐに受けてみようという気持ちになったわけではありせん。
同じ悩みをもつママ友に発達検査の経験者がいてくれたことで、話を聞いていくうちに一度受けてみようという気持ちになりました。
WISC(ウイスク)検査を受けてわかったこと
息子が受けたWISC(ウイスク)という発達検査では、同じ年齢の子どもたちと比較して知能の発達はどうなのか、得意・不得意な部分があるのかどうかを知ることができます。
息子の場合、同じ年齢の子どもたちに比べるとIQが少し低い81程度で、本人の能力の中でも得意な部分と不得意な部分との差が大きいことがわかりました。
本人の能力の中で、得意な部分と不得意な部分が大きいということはよく、発達に凸凹があると表現されます。
いわゆる、発達凸凹、発達グレーゾーンといわれるものです。
この発達の凸凹が大きいと、子ども本人は生きづらさを感じたり、フラストレーションを溜めやすく、癇癪起こしやすいといったことがあるとのことでした。
検査結果は母親とは別室で、息子本人にも小学生がわかりやすい言葉でかかれた説明の紙を見ながら施設の方がお話してくださいました。
息子自身、自分の能力のなかで得意な部分と不得意な部分の説明をうけ、どうな状況で自分が混乱しやすいのか、イライラしやすいのかを理解した様子でした。
まとめ
発達検査(WISC)を受けてみようと思ったのもも、実際に検査を受けるまでにはいくつもハードルがありました。
それについては、また別の記事にまとめようと思もいます。
一筋縄ではいかなかった発達検査(WISC‐V)までの道のりでしたが、私は受けて良かったと感じています。
もちろん、検査を受けたことで息子の癇癪が一切なくなったわけではありません。
これからも、程度や頻度の差はあれ、成長の過程で息子の癇癪とはうまく付き合っていく必要があると覚悟しています。
それでも、WISC検査を受けたことで、息子のことをこれまで以上に理解できるようになりました。
思ってもいなかった息子の不得意な部分がわかったことで、関わり方が確実に変わったことを感じています。
何より、ただのわがままのように感じてしまうことも多かった息子の癇癪が、本人の発達の偏りからくるイライラやモヤモヤが一因であることがわかったことで、少しだけ(本当に少しずつですが…)癇癪に寛容になれた気がしています。
母親である私も、思ってもいなかった息子の不得意な部分がわかったことで、関わり方が確実に変わったことを感じています。
何より、ただのわがままのように感じてしまうことも多かった息子の癇癪が、本人の発達の偏りからくるイライラやモヤモヤが一因であることがわかったことで、少しだけ(本当に少しずつですが…)癇癪に寛容になれた気がしています。
また、得意なことや苦手なこと、つまずきやすい理由がわかると、「こういうサポートが合うんだな」と関わり方のヒントが見えてきます。
結果の数字だけでなく、その奥にある“息子らしさ”を知るきっかけになったのが本当によかったと感じています。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
今後も息子が受けたWICS(ウイスク)検査について私が経験したことや乗り越えたハードル、癇癪やぐずりの対応としてこれまでにやってきたことなどを記事にしていこうと思います。
同じようにぐずり、癇癪の激しいお子さんをお持ちのみなさん!!!一人で抱え込まないでください!!!
ぐずり癇癪の対応は、本当に本当に神経が削られます。家事や育児以外にも仕事や家計のこと、パートナーとの関係など、日々神経をすり減らすことは他にもわんさかあります。
私の感覚では、母親が肉体的にも精神的にも疲弊しているときに限って息子の癇癪が頻発したり長時間が及ぶことが多いです…本当の地獄絵図です(涙)
まずは一人で悩まず、声をあげて助けを求めてください。
そして同じ悩みを持つもの同士、愛する我が子の癇癪とうまく付き合う方法をともに模索していこうではありませんか!!!!
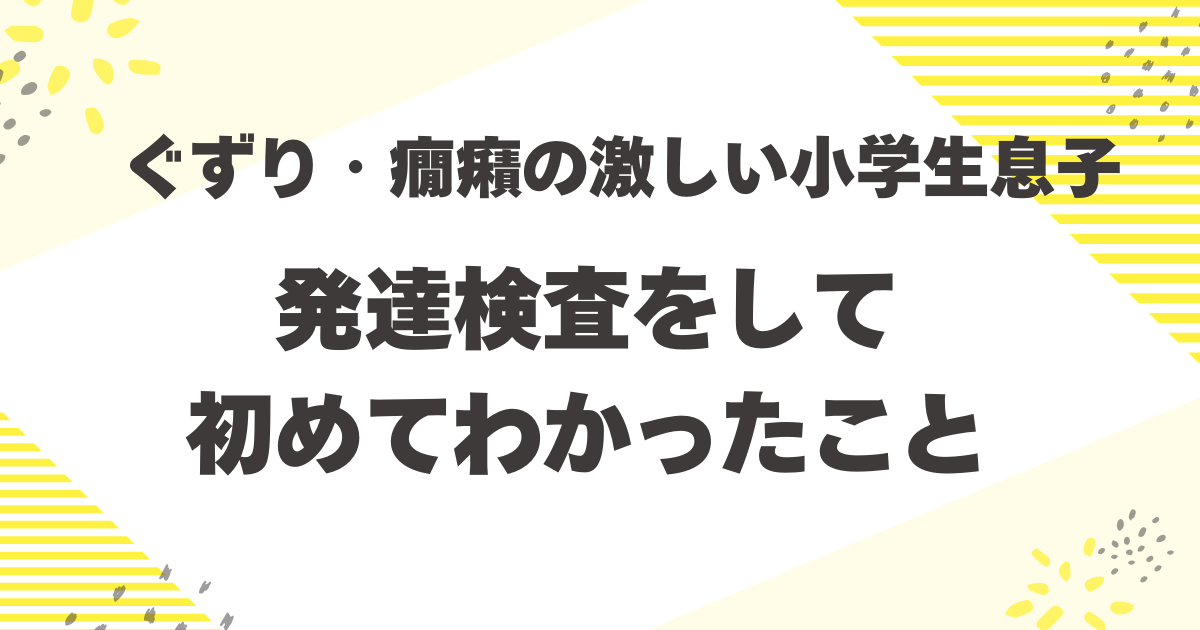
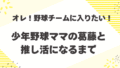
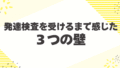
コメント